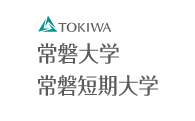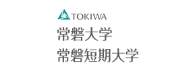水戸市主催「ヒューマンライフシンポジウム2022」に共催参加しました
![]()
![]()
![]()

会場となった水戸市役所本庁舎4階の会場には、本学学生を含め90名の市民が参加。同日オンラインで視聴された183名の方と合わせ273名の参加規模となった中、当日の司会を、茨城大学人文社会科学部現代社会学科3年生の長橋芽生さんと、本学人間科学部現代社会学科3年生の福島怜さんが務めました。

第1部 基調講演の様子

表情豊かに聴衆に語り掛ける安田菜津紀さん

司会を務めた茨城大学の長橋さん(左)と本学の福島さん(右)
第1部では、フォトジャーナリストの安田菜津紀氏が「共に生きるとは何かー難民の声、家族の歴史から考えた多様性―」と題して基調講演。
冒頭8,900万人という数字を提示し、今年2月に始まったウクライナ危機、さらに約10年遡り今も混乱が続くシリア危機に触れ、世界に日々難民が生みだされている状況を共有。
現地取材で丁寧に難民と向き合い、拾い集めた生の声を伝えると同時に、日本の難民認定の厳しい壁や日本社会に暮らす避難民の現実も紹介し、自身の出自と重ねて、多様な背景をもつ個人がそれぞれに尊重される社会の在り方を問いかけました。

第2部トークセッションの様子
前半では、茨城という地域がすでに直面している課題を、多文化共生やジェンダーの視点で検討し、とりわけ外国籍の子どもたちが、地域社会のセイフティネットからこぼれ落ちている現状に、「伴走していく支援」の重要性を確認しました。
後半の質疑応答では、「SDGsについて関心を持っていない人にどう伝えるか」との質問が取り上げられ、安田氏からは、「間口を広げ、好奇心をくすぐるような広がりやすい話題を選び、様々な人の関心に繋げてみること。」が具体例とともに提案されました。

ゲストスピーカーとして登壇した富田敬子学長
第2部終了後には、茨城大学、全国十大赌博官网から参加した学生の少人数グループを対象に、安田氏による出張ゼミナールが行われました。
参加学生は、事前に、モデレーターを務めた横溝准教授による準備打ち合わせに出席し、安田氏執筆の書籍を読んで参加。ジャーナリストを目指す学生、東日本大震災を目の当たりにした福島県いわき市出身の学生、社会科教師を目指す学生など、様々な背景や目標を持つ学生が、自分の体験や学びを土台に質問を投げかけました。
安田氏はそれぞれの関心?思いに寄り添い、一人で解決できないことは役割を分担することで対応する方法も提起。その場全体の対話が「未来につなぐメッセージ」として参加学生の心に刻まれました。

出張ゼミナールの様子