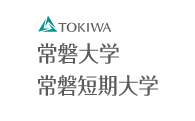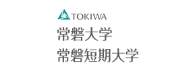学生が取り組むSDGs
ページ内目次
春セメスター:ミニプロジェクト
春セメスター:
ミニプロジェクト
QRコードを読み取ることで参加できるアンケートやポスターの作成、看板に直接シールを貼ることで、回答を可視化するアナログアンケートを実施しました。マイボトルの利用を促進することで、プラスチックごみの削減を目指しました。

正しいペットボトルの捨て方を広め、リサイクル可能な状態にして回収を促進するために、ポスター作成や呼びかけを行いました。また、学生対教員のゲーム形式で、楽しくペットボトルのリサイクルを推進する方法も取り入れました。

ポスターを2つ作成し、ゴミのポイ捨てに対する問題意識を高める活動を行いました。
また、大学内で実際にポイ捨てが行われている場所を確認し、その実態を把握しました。

不要になった服などを廃棄するのではなく、新たなアイテムに作り変える取り組みを行いました。実際に製作した作品を飾り、さらにポスターを通じて服の廃棄問題に対する意識を高めることに力を入れました。

実際に千波湖に赴き、3つのコースに分かれてゴミ拾いを行い、ゴミの量や種類を調査しました。また、千波湖でゴミ拾いをしているシルバーセンターの方に直接お話を伺い、取り組みについての理解を深めました。

秋セメスター:全体プロジェクト
秋セメスター:
全体プロジェクト






金銭的な不安を抱える常磐大生や、途上国で学びの機会が奪われている子どもたちを支援する。
使わなくなった教科書や参考書の行方から、「使う責任」について改めて考える。
教科書や参考書の「リユース」を通して、学びのバトンを受け渡す。

- ロゴの作成
- ポスターの作成
- イベント宣伝用の動画制作
- ホームページの作成
- インスタグラムアカウントの開設
これらの活動を通じて、イベントの認知度向上と参加者の募集を目的とした広報活動を展開しました。

- 回収ボックスの製作
- 本の分類表の作成
- 本の分類作業
- 栞の製作
- ビラの配布
これらの活動を通じて、イベントの準備や運営を円滑に進めるための実務を担当しました。

- 問題意識の整理
- 事前および事後のアンケート調査の実施とその結果のデータ分析
- 提供イベントのプレゼンテーション
これらの活動を通じて、イベントの効果を測定し、改善点を明確にするための調査と分析を行いました。



- 3年生のみで行う授業時間外の企画会議の実施
- 企画?運営班全体での昼休みの会議の実施
- 企画書や各種書類の作成
- 外部組織との連携?協力(「Study For Two」茨城大学支部と)
- 未配布の本の引き渡し→途上国の教育支援へ
これらの活動を通じて、イベントの企画立案から運営までを担当し、イベント全般が円滑に進むよう熱心に事にあたりました。

- 個人情報や汚れがないこと
- 落書きがないこと
- 10年以内に出版されたものであること
提供イベントは12月13日、19日、21日の3日間実施しました。趣旨に賛同し、その利用目的が明確な方に提供しました。
結果として集まった160冊のうち、
- 65冊を全国十大赌博官网の学生に寄付
- 95冊を「Study For Two」茨城大学支部に譲渡しました

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。